第8章 練習問題EXERCISE
練習課題に適した課題の条件は
・参加者がイメージしやすい
・専門的な知識を必要としない
この2つです。
実際にあつかいやすい練習問題をいくつか紹介します。
・ある商品(できれば特定する)をPRする方法を考える。
・あるお店(できれば特定する)のお客さんを増やす方法を考える。
・商店街(できれば特定する)の賑わいを取り戻す方法を考える。
・冬、雪が屋根に積もり雪下ろしをする際に発生する死亡事故を防ぐ方法を考える。
・高速道路で発生する逆走事故を防ぐ方法を考える。
・地方の鉄道路線を黒字化する方法を考える。
・地方の公共交通機関を便利にする方法を考える。
・農業を始める若者を増やす方法を考える。
・図書館の利用者を増やす方法を考える。
・小学校、中学校で落ちこぼれが出ない方法を考える。
・耕作放棄地の活用方法を考える。
・オレオレ詐欺をなくす方法を考える。
・虫歯予防を広める方法を考える。
詳細
「ある商品(できれば特定する)をPRする方法を考える。」
「あるお店(できれば特定する)のお客さんを増やす方法を考える。」
「商店街(できれば特定する)の賑わいを取り戻す方法を考える。」
できれば具体的な対象を特定したほうが盛り上がります。
似たような問題なので似たような答えが出ることが予想されますが練習としては連続して取り組んでもよいでしょう。
「冬、雪が屋根に積もり雪下ろしをする際に発生する死亡事故を防ぐ方法を考える。」
 雪国では屋根に雪が積もると雪下ろし作業をします。
雪国では屋根に雪が積もると雪下ろし作業をします。
雪下ろしをせずに雪が積もりすぎると家がつぶれてしまいます。
また、雪のあとに雨が降ると重くなるためさらに危険な状態になります。
しかし、この雪下ろしの作業で毎年何人かのひとが亡くなられます。
・屋根から落ちて頭や内臓を強く打って死亡する。。
・屋根から落ちて下にあった雪に埋まって動けなくなり凍死する。
・屋根から落ちた雪の下敷きになって生き埋めになる。
などの死亡理由があります。
「高速道路で発生する逆走事故を防ぐ方法を考える。」
一般道路でも発生していますが、高速道路は一方通行であるにもかかわらず逆走が発生して事故になるとそのスピードにより悲惨な事故、重大事故に発展するケースがあります。特に高齢者による事故が目立ちます。
「地方の鉄道路線を黒字化する方法を考える。」
 JRでも地方の路線はほとんどが赤字です。
JRでも地方の路線はほとんどが赤字です。
都会の黒字路線と新幹線の利益でそれを補てんして維持しているのです。
現在は公共性を理由に存続されていますが、中には廃線になる路線も出て来ています。
営業係数という数字があり、100円の営業収入を得るためにいくらの営業費用をかけているかという数字です。インターネットで調べるとほとんどの路線が厳しい状況であることがわかります。
JRだけでなく地方の私鉄も同様の状況にあり、そちらは黒字路線を持っておらず更に深刻です。
※都会のひとはイメージがわかないかもしれません。
「地方の公共交通機関を便利にする方法を考える。」
先ほどの課題とも関係しますが、地方では車社会です。
多くの人が自動車免許を持ち、通勤にも生活にも車で移動しています。
その結果、公共交通機関(電車・バス)を利用する人は減っています。
さらに、渋滞が増えてバスが遅延することもあり、バスを利用せずに自家用車で移動するという悪循環もあります。
高齢者は公共交通機関を利用したくても本数が少ないために車を運転し続け、運転能力が衰えても運転するのでこれによる事故も増えています。
「農業を始める若者を増やす方法を考える。」
現在、日本の農業は高齢化が進んでいます。
稲作は田んぼを所有する兼業農家がサラリーマンを引退して専業化した60歳以上が担っています。
しかし、次の世代は都会に流出しており20年後には担い手が不足すると考えられます。
機械も大型化して田植えや稲刈りは人手が少なくても出来るようになりましたが機械は高額です。
米価は下がっています。
野菜も価格決定権は主に市場(しじょう)にあります。
異常気象が多発し、天候によるリスクも高まっています。
グローバル化により海外の農産物とも競争しなければなりません。
以上によりサラリーマンの方が高収入ということもあります。
決まった休日はありません。早朝の仕事もたくさんあります。
一方で成功している若い農家も見られます。
自分で消費者を探して直接取引をしているひと、6次化をすすめて加工品を販売し利益を出しているひともいます。
農業をやりたいと思う若者もいますが実現できずにいるひとも見られます。
・土地がない
・資金がない
・知識がない
(土地の特性などもあって一般的な農業のやり方が使えないことがあります)
・収入が見込めない
などの理由があります。
「図書館の利用者を増やす方法を考える。」
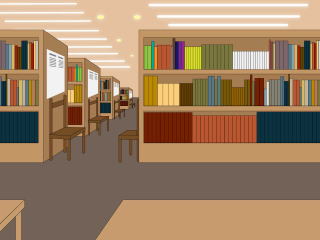 本を読む人が減っていると言われています。
本を読む人が減っていると言われています。
図書館の利用に限って言えば利用者数、貸出数は増加しているようですが、若い世代に利用状況を聞くと、ここ1年で図書館を利用したかという問いにおよそ8割が利用していないと答えます。
一部の人の利用、特に仕事をリタイアした世代の利用が多いのではないかと考えられます。
若者はインターネットなどで情報を得られるようになりました。
若者は読書ではなくインターネットゲームや動画サイトなどの娯楽に時間を費やしているようです。
市町村合併によって1つの市町村が複数の図書館を運営しているケースも多数あります。
指定管理制度を利用して公立の図書館を民間企業に運営させるケースも増えています。
その中にはカフェなどを併設しているものもあります。
新潟県長岡市の状況
館数 10館
蔵書 87万冊
館外貸出数 162万回/1年
利用者数 3万8千人/1年
長岡市人口 28万人
新規購入数 4万冊/1年 (購入金額6500万円)
「小学校、中学校で落ちこぼれが出ない方法を考える」
日本では義務教育の過程で飛び級も留年もほとんどなく、同じ仲間で進級できる一方で、充分な学力を身につけていないのに進級してしまい、あとの授業に全くついていけず落ちこぼれてしまう生徒がいるようです。
芸人さんが探偵になって何かをスクープする関西のテレビ番組で、歳の離れた弟が九九を勉強しているけど、社会人の自分は九九が出来ずに簡単な計算も計算機をつかっているので九九を覚えたいという依頼がありました。
「耕作放棄地の活用方法を考える」
耕作放棄地が増えています。
米の消費が減少しています。
里山に住む人も自分の土地で米をつくるよりもサラリーマンとしてお金を稼いで米を買う人が増えています。
減反政策のなかで山奥の田畑、急斜面の田畑が減反の対象となり、耕作しやすい平地の田畑のみが使われてきました。
里山が維持できずに山の自然と人里との緩衝地帯がなくなったことによって野生動物(熊、猪、猿など)が人里に出没し、人が襲われる事故が発生しています。
「オレオレ詐欺被害をなくす方法を考える」
オレオレ詐欺が広まってから何年も経ち、認知度も上がっているはずですがいつまでたっても被害はなくなりません。
「虫歯予防をひろめる方法を考える」
虫歯で歯医者さんにかかるひとはたくさんいます。
虫歯を予防するには歯を磨くことだとわかっているはずなのに虫歯になるひとはいなくなりません。
- 練習しましょう
 ブレインストーミングセミナーは吉越戦略研究所
ブレインストーミングセミナーは吉越戦略研究所
お気軽にお問い合わせください。
バナースペース
吉越戦略研究所
〒945-0306
新潟県刈羽郡刈羽村十日市2190
TEL 090-2778-9202
facebookpage http://www.facebook.com/yslaboratory